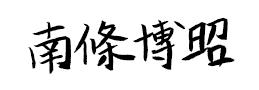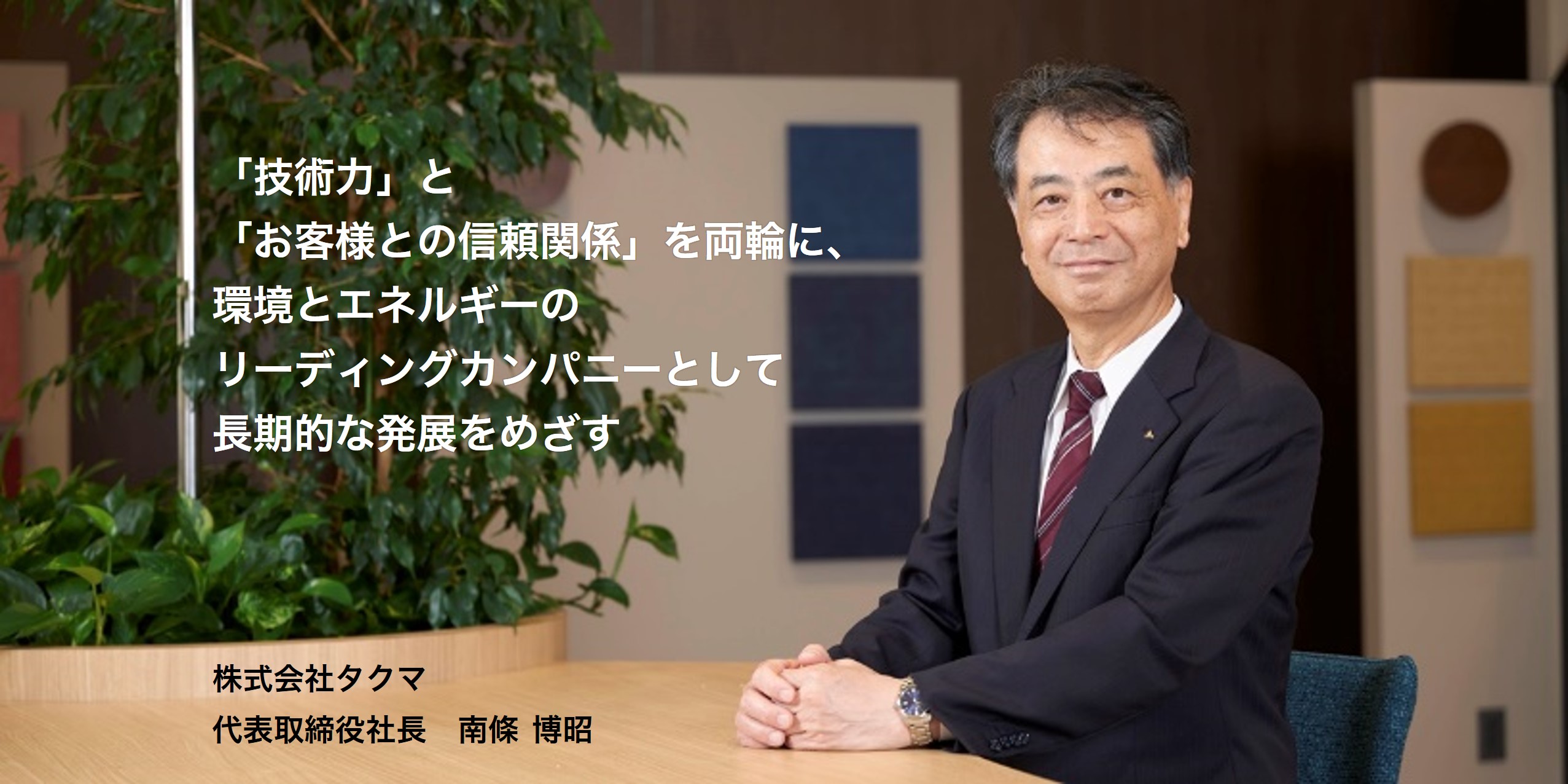
タクマグループは、中長期の経営方針として長期ビジョン 「Vision 2030」を策定し、その実現に向けたファーストステップとして、2021年4月より「タクマグループ第13次中期経営計画(2021~2023年度)」をスタートさせました。経営基盤の強化により、各事業において従来のビジネスの一層の強化を図ると同時に、将来の環境変化への対応を加速させて、持続的な成長をめざしています。
同中計の2年目となる2022年度においては、受注高は期首目標を若干下回ったものの引き続き高水準となりました。受注済みプラントの建設工事が順調に進捗したことから、売上高は前期比85億円の増加、損益面においては、売上高の増加に加え利益率の改善により、営業利益は前期比38億円増加の138億円、経常利益は40億円増加の146億円、親会社株主に帰属する当期純利益は21億円増加の96億円となりました。
また、2023年1月に播磨新工場が操業を開始しました。新工場はボイラの大型化、高温高圧化など、多様化するお客様のニーズに応え、高品質なモノづくりの方針を継承し、生産性と品質をさらに高めるとともに、環境性能と防災力を向上させた、人・環境にやさしいサステナブルな生産拠点です。播磨工場の80年にわたる歴史を引き継ぎ、伝統に新しい生産技術を融合させた、新たな時代にふさわしい新工場となっています。新工場の建設においては、行政との許認可の調整、生産設備の配置計画や手配、旧工場での生産を継続しながら新工場への設備の移設などに加え、新型コロナウイルス感染拡大への対応や建築資材の高騰、建設業の人手不足など、さまざまな課題がありましたが、関係者様のお力添えと社員一人ひとりの創意工夫、努力により、着実に解決していきました。この新工場建設に携わった貴重な経験は、今後の業務遂行のさらなる向上につながると考えています。
現在、私たちはさまざまな社会課題に直面しています。中長期のトレンドにおいては、グローバルな課題として、気候変動問題の深刻化、人口の増加・新興国の経済成長にともなうエネルギー需要の増加等があり、また国内では人口減少・高齢化による内需の縮小、人材・担い手不足や国・地方自治体の財政の逼迫、公共インフラの老朽化などがあげられます。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響やロシアによるウクライナ侵攻は、持続可能な社会の実現について不確実性を高めました。このような状況においても、将来に向けて持続的な成長をいかに実現していくかが重要な課題です。
明治大正期の十大発明家でもあった田熊常吉は、1938年にボイラを通じて社会へ貢献するという「汽罐報国」の精神を掲げ当社を創業しました。以来、タクマグループは、この精神を継承し、あらゆる種類のボイラを手がけるとともに、ボイラで培った技術を生かして廃棄物処理プラントや水処理プラントなどの環境衛生分野へ進出し、エネルギーの活用と環境保全の分野を中心に事業を広げ、社会の発展と課題解決に貢献してきました。
当社の経営理念「世の中が必要とするもの、世の中に価値があると認められるものを生み出すことで、社会に貢献し、企業としての価値を高め、長期的な発展と、すべてのステークホルダーの満足をめざす。」はこの創業の精神にあり、事業活動を通じて社会の長期的、持続的な発展に貢献することが、当社グループの原点であり、変わらぬ価値観です。
この価値観の下、製品・サービスの改良・改善を積み重ねて蓄積してきた技術・ノウハウと、アフターサービスやソリューションの提供等による長年にわたる真摯なお付き合いを通じて培われたお客様との信頼関係が、有形無形の財産として脈々と引き継がれ、当社グループの強みとなり、競争力の源泉となっています。
当社グループは事業活動を通じたESG課題への取り組みを強化し、すべてのステークホルダーの満足とグループの持続的な成長をめざすESG経営を推進しています。
当社グループの2030年にありたい姿を示した長期ビジョン「 Vision 2030」において、「ESG経営の推進によりお客様や社会とともに持続的に成長し、再生可能エネルギーの活用と環境保全の分野を中心にリーディングカンパニーとして社会に必須の存在であり続ける。」ことを掲げています。再生可能エネルギーの導入拡大による環境負荷の軽減は、気候変動対策上不可欠です。特にバイオマスや未活用の廃棄物を燃料とする発電は、天候の影響を受けず安定的に電力供給をすることができるうえに、廃棄物の再利用や減少につながるため、循環型社会の構築にも大きく寄与します。当社が提供するバイオマス発電プラントと一般廃棄物処理プラントにより、バイオマス・廃棄物をエネルギーに変換するで、二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量削減と電力の長期安定供給の両面で貢献していきます。
当社の持続的成長には、各部署、現場を支える人材の活躍が必須です。これを実現するために、2023年6月、「人材の育成に関する方針」と「社内環境整備に関する方針」を定めました。ダイバーシティを推進し多様な人材を活用することで、事業環境の変化に柔軟かつ迅速に対応することが可能になります。多様性をお互いに認識し、尊重することにより、組織が多様な人材を受け入れ、その能力を発揮して、適材適所で活躍できる環境を整備します。一人ひとりが当事者になり、仲間としてしっかり向き合い、本音で目的を共有し、徹底した議論を通じて決まったことを全員が実行する職場を作り、成長と競争力の強化につなげます。
当社グループを取り巻く事業環境は、先行き不透明な状況が続くと予想される中で、一瞬の油断が経営の根幹を揺るがす事態になる可能性があります。このような事態に直面したとき、立ち返るべき軸となるのが当社の経営理念です。経営理念を大切にしながら仕事をしているか、経営理念に照らして物事を判断しているか、といった視点を持つことが、組織を正しい方向に導くとともにパフォーマンスの向上にもつながります。経営理念を組織に浸透させることにより、社会課題の解決と収益力の向上を両立し、社会と会社の持続的成長を実現していきます。
当社は、2006年から国連「グローバル・コンパクト」※1に参加しており、4分野(人権、労働、環境、腐敗防止)10原則を支持しています。これらの世界共通の理念を理解、尊重しながら、事業を展開していきます。また、当社グループは、再生可能エネルギーという言葉がまだ一般的に使われていない時代から、廃棄物、バイオマスを利用した高効率発電など、温室効果ガスの排出量削減技術で社会課題の解決に貢献
しています。国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」※2や、COP21の「パリ協定」への取り組みは、当社グループの事業と非常に親和性の高いものと考えています。
当社グループの活動が、社会課題の解決、社会の持続的発展に貢献できるよう、皆さまからのご意見を真摯に受け止めてまいりますので、忌憚のないご意見、ご指導を賜りますようよろしくお願いいたします。

※1 国連「グローバル・コンパクト」:タクマグループは、国連グローバル・コンパクト(UNGC)に参加しています。国連グローバル・コンパクトは、各企業・団体が責任ある創造的なリーダーシップを発揮することによって、社会の良き一員として行動し、持続可能な成長を実現するための世界的な枠組み作りに参加する自発的な取り組みです。

※2 国連「持続可能な開発目標(SDGs)」:国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」でも掲げられた、地球環境にとって重要なこれらの課題の解決に向けて、当社はさまざまな技術を駆使して実現しています。
2023年7月
代表取締役社長