
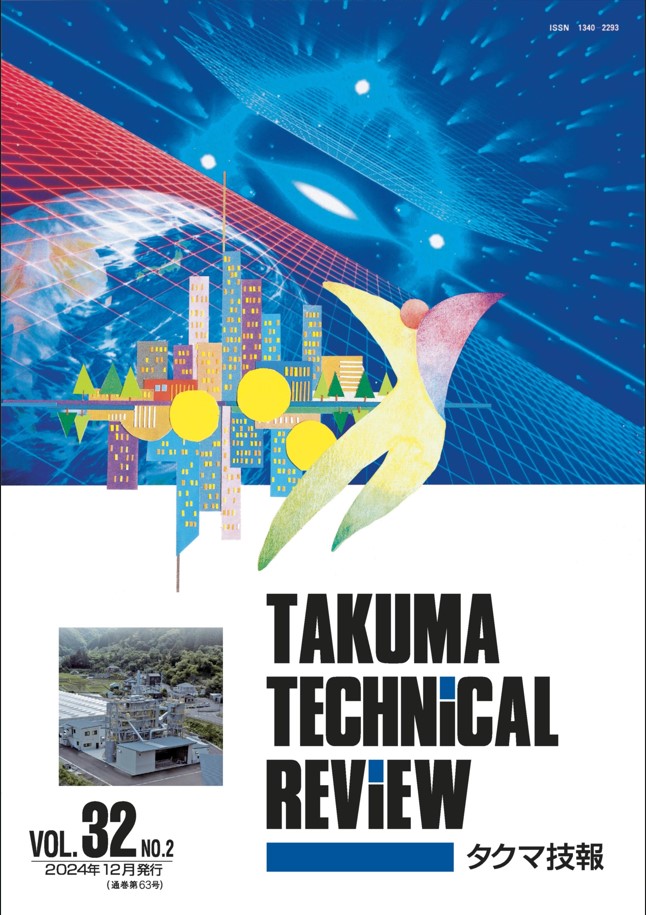
(要約)
階段ストーカ式ごみ焼却炉内の燃焼現象は非常に複雑であるため,未解明な部分が多く,将来的なごみ質の変化や環境規制の強化に対応する上で,より詳細な現象理解に基づいた燃焼技術が求められている。本稿では,各種光学計測手法の紹介と階段ストーカ式ごみ焼却 炉内のガス流速,温度,化学種分布計測および炉内観察への適用について解説する。この光学計測手法は,従来のサンプリングや熱電対等による各種計測に比べ時間・空間分解能に優れた特性を持つほか,非接触であるため燃焼場を乱すことなく計測ができるメリットがある。
(要約)
日本は循環経済を社会課題の解決と経済成長を両立させる手法として国家戦略に位置づけている。循環経済への移行に向けて両輪となる戦略が経済産業省の「成長志向型の資源 自律経済戦略」と,環境省の「第五次循環型社会形成推進基本計画」であり,この戦略に基づき日本は循環経済への移行に取り組むこととしている。循環経済へ移行するには動脈産業と静脈産業が資源の効率的な循環で連携する必要があり,循環経済に適したバリューチェーンの構築が求められる。なお,資源を循環させても発生する廃棄物の適正処理として,サーマルリカバリーも重要な手段である。
(要約)
バイオマス発電において,燃料の安定調達は既存発電所の運転維持だけでなく,導入量の拡大の観点からも大きな課題である。そのため,多様なバイオマス燃料を取り扱うニーズが増加しており,FIT・FIP 制度の追加認定燃料を中心に今後の利用が見込まれる新規燃料を探索し,その特徴や燃料利用上のポテンシャルを調査した。バイオマスは種類によって性状が大きく異なり,生産地や加工条件の違いなども考慮した評価が必要である。新規燃料を利用する上では,事前に各種の分析によりその特性を把握し,課題を抽出することがプラント計画の最適化には重要である。今後も草本系の資源作物や早生樹など多様なバイオマス燃料の利用が拡大していく可能性は高いことが予想され,その利用に向けて燃料の性状やボイラー設備への影響を把握するための分析方法についても検討した。
(要約)
廃棄物発電の高効率化には,ボイラー蒸気の高温化が重要なファクターの一つである。高温の蒸気を作るボイラーの過熱管は腐食性を有する高温のガスに曝されるとともに,その表面には種々の塩を含む燃焼灰が付着するため,蒸気温度の高温化にともない腐食が促進される。そこで,実機の過熱管表面に付着した燃焼灰を採取し,その燃焼灰を用いて,灰に温度勾配を付けた燃焼灰埋没試験をおこない,過熱管に使用される耐熱鋼の初期の高温腐食挙動を調査した結果について報告する。
(要約)
逆送移床ストーカ式バイオマスボイラーにおいて,燃焼排ガス中のダストには比較的多くの未燃分が含まれている。当社では,燃焼効率の向上の観点から,未燃分は分離回収して炉内に返送することが多い。燃焼排ガス中のダスト回収のためにマルチサイクロンを設置しているが,機器の圧力損失が大きいこと,およびマルチサイクロンの損耗が課題となっている。そこで,これら課題を克服できる集じん装置としてルーバー式集じん装置の開発を進めており,実ガスによるベンチスケール試験を実施した。本試験において,マルチサイクロン以上の未燃分回収性能を得られる条件が判明したため,試験の概要と結果について報告する。
(要約)
2012 年に再生可能エネルギー特別措置法に基づく固定価格買取制度がはじまり, 2015年に 2 MW未満の間伐材等木質バイオマス発電に対して 40 円/ kWhの優遇された買取価格区分が設定された。これを受け当社では本区分向けに全国に適用可能な 2 MW 級木質バイオマス発電設備の商品化をおこない,2018 年に 2 物件を納入し,現在では延べ 15 件の受注数に及んでいる。本稿では,当初の商品化以降の再生可能エネルギー特別措置法の制度の変遷や2 MW 級木質バイオマス発電設備を取り巻く環境の変化を説明するとともに,それらに対応した設計変更点の紹介,その他設備改善点などを報告する。